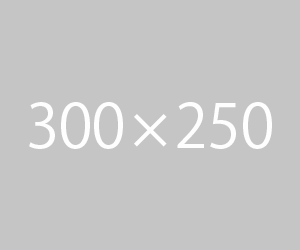【着物TPO小話】意外と知らない~色無地って何?~

こんにちは!
着物通販サイト「着物とみひさ」です。
今日の話題は「意外と知らない~色無地って何?~」
ということで、色無地という着物についてご紹介していきます。
【色無地とは】
色無地とは、黒以外の一色で染められた無地の着物のことです。
着用シーンの幅広い着物で正式なお祝いの場などにも着ていけるため
とても便利な着物です。
また、家紋を入れる数によっても格式が変わり
着用シーンも変わってきます。
シンプルながらも地紋の柄や色のチョイスに
誂える人のセンスが出るおしゃれな着物です。

【色無地の歴史】
江戸時代末期、庄屋のお供をする使用人の女性・子供たちは改まった場では
必ず紋付の色無地を着用していました。
その後大正時代になり紋付の色無地は、礼装とされ現在の留め袖や振袖と同じ格式とされるようになります。
庶民の間でも色無地が着用されるようになったのは昭和に入ってからで
戦後、教育制度の普及に伴い卒・入学式に参加する母親が着用する着物としての
着用が目立ち始めました。
現在では、シンプルで派手すぎないことから
侘び寂びの文化を重んじる茶道の世界では重宝され
一つ紋を入れると略礼装になるため場を選ばない着物として人気があります。
【色無地の着用シーン】
色無地の着用シーンは幅広く
紋の数で着用できる場も変わってきます。
紋の数による着用シーンは
一つ紋・・・結婚式(友人)、パーティー・お茶会など。
三つ紋・・・結婚式(友人)、パーティー、弔辞(色次第)
五つ紋・・・留め袖に次ぐフォーマル。結婚式、式典など
紋なし・・・お稽古事、食事会、帯次第で結婚式(友人)
となっています。
【色無地のおしゃれ】
色無地はシンプルながらも
地紋の模様や紋の入れ方で
グッとおしゃれ度の上がる万能着物です。
紋も最近では家紋ではなく自分で作った紋を入れる方もいます。
選ぶ色や地紋の模様にも
誂える人の好みが反映されます。
こちらの着物は、きれいな山吹色に
いろいろな柄が地紋として施されたとてもおしゃれな一枚です。

影紋ですが一つ紋が入っているので
お茶会など幅広く着用できますよ。


袋帯を合わせてフォーマルにも着られる便利な一枚です。
【便利な着物「色無地」を楽しもう】
今日は色無地についてのお話でしたがいかがでしたか?
着用シーンの幅広い着物、色無地。
お気に入りの色の色無地が一枚あると
着物生活が楽しくなりますよ!