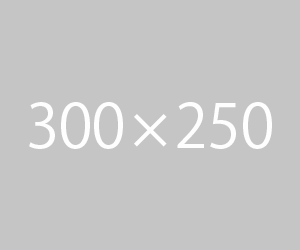【着物TPO小話】意外と知らない~小紋って何?~

こんにちは!
着物通販サイト「着物とみひさ」です。
今日の話題は「小紋って何?」です。
普段着の着物を始めようと思ったときに、着物の種類がたくさんあって迷ってしまう方も多いのではないでしょうか?
今回はそんな普段着着物初心者さんへ向けた内容となっています。
【小紋とは】
小紋とは、着物の上下に関係なく同じ模様が同じ方向に柄付けされた普段着の着物です。
全体に細かく模様が入っていることが名前の由来です。
小紋の中にもいろいろ種類があるのですが、ざっくりとわかりやすい言い方をすると
「総柄ワンピース」のようなイメージです。
普通の小紋は街着・普段着という格式なので、正装としての着用はしません。


【江戸小紋とは】
江戸小紋とは型染の小紋で全体に細かい柄が入っており遠目には無地のように見えるのが特徴です。
小紋の中でも格の高い着物で、柄が細かいほど格が高いといわれています。
街着としても着用できるため汎用性の高い着物ですね。
江戸小紋の柄付けには江戸小紋三役・五役と呼ばれるものがあります。
江戸小紋三役と呼ばれる柄は、鮫・行儀・角通し
五役は三役のほかに、大小あられ・万筋を足したものです。
この中でも鮫柄は特に格が高く、極鮫に紋を入れると訪問着と同格とも言われています。
江戸小紋の歴史は、名前の通り江戸時代。
元々は武士が裃(かみしも)の柄付けを競い合ったことに始まり
それで柄が細かくなったといわれています。
特に細かい柄のものには”極(ごく)”とつきます。
藩はそれぞれに腕のいい職人を囲って、柄の細かさを競い合ったという説もあります。
贅沢を禁じられていた江戸時代に、遠目には無地に見えて近づくと模様が入っているという
武士や町民の洒落心から生まれたのが江戸小紋です。
【飛び柄の小紋とは】
飛び柄の小紋は、小紋の中でも柄の間が広くとってあり飛び飛びに模様が入った小紋を指します。
こちらの着物も普通の小紋よりも格が高くなります。
付け下げと小紋の間くらいの格と思っておくと良いでしょう。
礼装用の袋帯を合わせると控えめなセミフォーマルになるため、カジュアルなパーティーや卒・入学式などに良いでしょう。
飛び柄の小紋はシンプルですっきりとした柄付けなのでコーディネートがしやすく、また長く着られる着物です。
柄の間隔が広いため無地の部分が多く、年齢に合わせてコーディネートすることができるでしょう。
普段着~セミフォーマルとこちらも汎用性が高いため、一枚あると着回しがききますよ。

【知って得する”小紋”のお話】
今日は普段着の着物”小紋”についてのお話でした。
普段着の中にもいろいろな種類があり、柄によって様々な格式があります。
いろいろな名称を耳にして迷って尻込みしてしまう方にも
「着物は怖くない!」ということを、これからもお伝えしていきたいと思います。